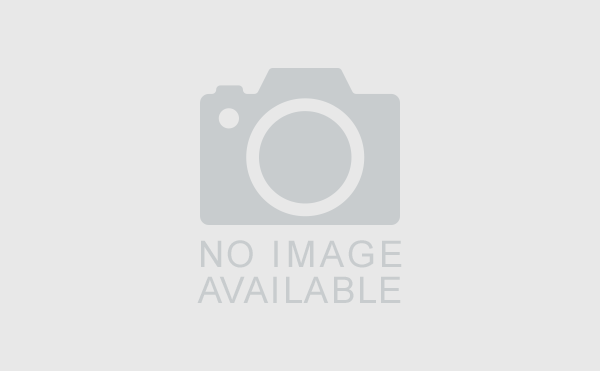『トスカーナの贋作』とフレーム内フレームとしての窓
アッバス・キアロスタミの『トスカーナの贋作』は、見るものを幻惑する構成を持っている。元より虚実の境界を脱臼させることにかけて秀でた監督である。職業俳優を主演に迎えて撮った、フィルモグラフィにおいては異例なこの作品においてもそれは例外でない。とは言え、この作品がノンリニアな時系列を呈するわけでもないし、第四の壁を破ってみせたりすることも特にない。手口はいつもながらシンプルで狡猾だ。
中心となるのは妙齢に差し掛かった2人の男女である。片方は英国人の男性作家で、美術の真贋性というものに関する一般的な常識感覚──本物は価値があって偽物には価値がない、といった至極単純な──を転倒させるような批評本を最近上梓したらしく、刊行記念の講演会が催され、そこにもう片方の主役である女性の美術商も訪れている。成り行きで2人はトスカーナの街並みを散策するが、途中で立ち寄ったカフェにおいてたまたま夫婦と間違われたことをきっかけに、あたかも長年連れ添った夫婦であるかのようなロールプレイング/ごっこを始める。
一気に掴まれたのは、カフェでジュリエット・ビノシュ(美術商)が涙を流す瞬間だった。役者が涙を流して見せる瞬間なんて、映画の中には無限と言っていいほどある。もはやそれを見ていていちいちどうとも思わない(しいて言えばこの泣き方はうまいな、とか練習したのかな、などとぼんやり考えるぐらいだ)ほどにはありふれている。しかし、ここでの涙には何か虚を突かれたような、あ、ほんとに泣いてる人を見てしまった、というような驚きがあった。それを感動と呼んでも間違いではないかもしれない。重要なのは、物語やキャラクターに感情移入していたから心を動かされたわけではないということだ。というのもこのシーンでジュリエット・ビノシュが泣き始める理由はその時点においてよく分からないからである。それよりも人がふっと泣くということ、それを目撃してしまった感覚にこそ全てがある。映画における共感と感動とは、それぞれ似て非なる相貌をしている。
しかしだ、とここで観客の思考は自らを足止めする。贋作とタイトルに銘打たれた通り、しつこいぐらい俳優同士の会話の中でも強調されている通り、この作品のひとつのテーマは偽物である。ここでのジュリエット・ビノシュの涙は結局のところ演技に過ぎない。涙が涙であることに変わりはないのだが、やはりそれは虚構である。いや、事態はむしろ逆であって、虚構ではあるのだが涙は涙なのだ、というほうが正しいのだろうか。映画に映っているものは、それがカメラによってとらえられた光景である限り、すべて真実であるとも言えるのだし……と、観客は画面に映っているものの真贋性をめぐって思考を始めざるを得ない。そこに映っているのは、情報の混乱も、時系列の奇矯な編集も介在しないシンプルな男女の会話劇に過ぎないのだが、後半に入って彼らが「ごっこ」を始めると事態は一層謎めいていく。ここで彼らが行っている/いま私が目撃しているものは一体何なのか? という問いが、フィクションとリアリティ2層のレイヤーにまたがって展開する。「演技」に引き寄せられ、時に激しく心を揺さぶられる映画というものの奇妙さにただただ困惑するばかりだ。終盤に至ると、まるで彼らの足取りが迷宮の中に踏み入っていくようでもある。『去年マリエンバートで』のような持って回った語りを経ているわけでもないのに。
優れた映画を見ていると、決まっていつも似たようなことを思う。どうしてこんなシンプルにこれほど複雑なことができるのだろうか? という問い。単純さと複雑さというのは、たぶん対立概念ではないのだ。
ところで本作はエンドロールに至ってもなお人を食った仕掛けが施されている。映画のラストショットは開け放たれた窓なのだが、この窓の上限と下限でちょうどエンドロールの文字が切られている。つまりエンドロールが窓の外側を流れている(窓の枠組みによって文字が遮られている)かのように見える。画面に浮かぶクレジットのたぐいの文字情報は、通常映画の世界に対して上位に存在するものと見なされている。だからこそ画面を覆って観客に働きかけてくるわけだが、その関係性が逆転することで、ここでも虚実が転倒している。
奇妙なエンドロールが通り過ぎていくのを眺めながら何となく連想したのは、これもまたメタフィクショナルな仕掛けが全編に展開するバスター・キートン『探偵学入門』の結末だった。虚構内虚構の夢から現実に戻ってきたキートンは、目の前で上映されている映画=スクリーンの真似をして女性との関係を築こうとする。スクリーンの四角と、映写室の小窓が何度もカットバックされ重ね合わせられる。ここでスクリーンと映写室の窓が並置されるのは、四角形という図像が類似していること以上の意味がある。虚構から現実へ引き戻された自分を再び虚構へ接近させるため、キートンは窓というスクリーンを必要としていた。
思えばリュミエール兄弟の時代から、映画は窓ないし扉といったモチーフに引き寄せられてきた。空間を四角く区切るという特性が、カメラに、ひいては映画そのものに酷似しているからだろう。わけても映画という枠組みの中にもうひとつの枠組みを重ねた二重フレームの構図は、メタフィクショナルな可能性に通じる窓となるようである。